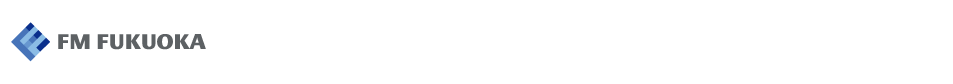メシュラングルメ研究所です!!
様々な食材に関して、研究、新たなメニュー開発を
していこうじゃないかというコーナーです。
今週から、新しい研究に入ります。
それは、海苔です!!
ということで、今回は海苔について詳しくなろうと思います。

実は私、先日、柳川市に行ってきて、海苔について調査してきました。i
あまりご存知ない方もいると思いますが、柳川市は海苔の生産が盛んなんです。
そこで、柳川市役所の方、元海苔漁師の方などから、色々お話を聞いてきました。
日本の海苔の生産量
75億枚と言われています。
そのうち、佐賀県で18億枚、福岡県で12億枚、熊本県で8億枚、
なんと、半分以上は、有明海で生産されています。
金額にして福岡県は150億円で、5年連続2位、そのうち柳川市は120億円です。
ちなみに、佐賀県は220億円で、15年連続で日本一です。
海外の海苔の生産
実は最近韓国が盛んで、100億枚以上生産されています。
日本にも多く輸入され、スーパーなどに並ぶ海苔などに加工されています。
海苔の養殖
大昔から海苔は食べられていて、大宝律令にも奉納したという記録が残っています。
ただし、この時は岩についた海苔を削り取ったもの。
養殖できるなったのは、イギリスの学者のある発見がきっかけです。
冬場にできる海苔は、夏場にどこに隠れているのか?
それは、牡蠣の殻の中にいるということを発見したのです。
その発見をもとに、柳川市では大正13年(1924年)から養殖が始まりました。
以前は、東京での養殖が盛んで「アサクサノリ」が有名ブランドでした。
これは東京の地名というだけではなく品種名でもあります。
それが、日本の海洋開発がすすみ、水質が変わっていったことにより、
昭和の中頃から有明海の海苔が注目を集めるようになりました。
有明海で作られる海苔の品種は、「スサビノリ」になります。
柳川(有明海)でできる海苔の特徴
海苔の養殖法には「支柱式漁法」と「浮き流し漁法」があります。
「浮き流し漁法」は、海苔がずっと海水に浸かったままの状態で養殖されます。
有明海では、最大6mにもなるという潮の干満の差を利用した「支柱式漁法」を採用。
海水に使っている間は海の栄養を取り、水面から出たら太陽の光を浴びる
ということを繰り返すことで、柔らかく、口溶けの良い海苔になります。
有明海で作られる海苔の大半は、●●に使われている。
大手コンビニ3社のおにぎりは、ほとんどが有明海でできた海苔を使っています。
有明海でできた海苔は、おにぎりに直巻きすると、溶けてしまいます。
そこで考え出されたのが、フィルムを使って、食べる直前に巻く方法です。
そのため、コンビニおにぎりの海苔は、パリッとしている上に、
噛み切りやすいのです。
さあ、来週も海苔の話をしますよ。