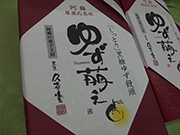銘菓『ゆず萌え』を製造、販売する和菓子店『菓匠 久幸堂』の二代目、青木幸治さん。今から11年前に青木さんが考案したという『ゆず萌え』は、黒砂糖入りの生地に、柚子ジャム入りの白餡を包んだ一口サイズの饅頭で、『全国菓子大博覧会』で『名誉総裁(寛仁親王)賞』を受賞した他、阿蘇市で開かれた『全国育樹祭』では、皇太子殿下のお茶菓子に選ばれるなど、阿蘇を代表する銘菓として多くの人々に愛されている。
「この『ゆず萌え』は、しっとりとした皮の食感と、上品な餡の甘味、そして、柚子の爽やかな香りが特徴で、口に含んだ時の一体感を生み出すまで、何回も試行錯誤を繰り返し、ようやく完成したモノなんですよ」。そう語る青木さんは、高校卒業後、当時、日本一と呼ばれた東京の洋菓子店の師匠に師事。店の休憩室に泊まり込みながら腕を磨き、『ゆず萌え』を生み出した技術の礎を築いたという。
「もともと実家は煎餅屋だったのですが、これからの時代は洋菓子だろうと洋菓子店で修業させてもらったんですよね。しかし昼間は雑用ばかりで、腕を磨くことが出来ませんでしたから、皆が帰った後にこっそりと実技を勉強したり、店にあったとても自分の給料では買えないような、お菓子の本を読んだりして勉強しました。おかげで普通は基本を習得するまで3年かかると言われていた修業も、2年弱で終えることができたんですよ」。そうした努力が師匠に認められ、洋菓子の本場であるフランス行きを勧められた青木さんだが、早く帰ってきて欲しいという父親の要請により断念。しかし阿蘇に帰郷してから数年後、諦めきれずに単身、フランスに渡ったという。
「その時はお土産用のケーキなどを作っていたんですが、これが全然、売れなくて。東京の名店帰りということで天狗になっていたんでしょうね。そんな時にフランスに渡ったのですが、フランス人から『日本には和菓子というすごい文化があるじゃないか。それなのになぜ洋菓子にこだわるのか』と言われ、衝撃を受けたんですよ」。そうして帰国後、和菓子職人や小豆の生産者などに教えを乞い、本格的に和菓子の製造を始めたという青木さん。そして遂に、そんな努力の結晶である『ゆず萌え』が完成。その『ゆず萌え』は、地元の人々から長年、変わらぬ味として愛されている。
「この『ゆず萌え』が完成してから11年が経ちますが、実は作る技術は年々、進化しているんですよ。どんな料理でも何回も食べていると飽きてきますよね。それでも前と変わらずに美味しいと言われ続ける為には、技術が進んでいなければならないんです。よく料亭の方などから話を聞くのですが、やはり常に努力し続けているからこそ、いつ行っても前と変わらない味が提供できるというんですよ。変な話、前と変わらずにまったく一緒の技術でしたら、その美味しさを保てないと私は思っています。ですからこの『ゆず萌え』は、変ったという風に言われたことは殆どないですね」。どんなに美味しいモノでも、何度も食べていると最初の感動は薄れてしまう。飽きられることなく何度食べても感動してもらえるように、美味しく進化しているからこそ、『ゆず萌え』は阿蘇の銘菓となりえたのだろう。
「この『ゆず萌え』を作って一番嬉しかったのは、ある日、お婆ちゃんがトコトコと乳母車を押しながら店まで歩いてきて、『ありがとうございます』と、『こんなに素晴らしいお菓子を、他所に胸を張って持っていけるモノを作ってもらって、誇りに思います』と言って下さったんですよね。この『ゆず萌え』は多くの地元の人々に助けられて完成した、また水害で作れなくなった時期があるなど、本当に様々なストーリーのある商品ですから、地元の人に、そんな言葉をかけてもらえるなんて、嬉しくて言葉になりませんよね」。現在は、そんな『ゆず萌え』を、さらに進化させた『いも萌え』という芋餡をベースにした新商品を開発するなど、その進化のスピードを緩めることのない青木さん。
「我々が作っているのは単なる菓子ではなく、阿蘇の菓子文化なんです。文化となる為には一代で終わるようなモノではなく、二代、三代と受け継がれるモノでなくてはなりませんよね」。そんな想いで作られた『ゆず萌え』は、これからも進化しながら変わらぬ味として、いつまでも阿蘇の人々に愛されていくことだろう。
| 前のページ |