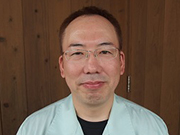『Kirafte(キラフテ)』のブランド名で、木の靴べら専門店を展開する工房『ウッドクラフトかづ』の代表、宮原一暢さん。天領であった江戸時代から木材の生産地、集積地として栄え、現在も全国有数の木工製品の産地である日田市で、クラフトを木と手で作るという意味を込めた『キラフテ』の名の通り、機械では不可能な手加工により、美しいフォルムと機能性を両立させた木の靴べらを製作する。
「子どもの頃からモノ作りが大好きだったんですよね。両親に買ってもらったサンダーバードのプラモデルにハマり、以来、蒲鉾の板で椅子や机などを作って遊んでいたんですよ」。そんな宮原さんは実家が北九州市の開業医であった為、大学は医学部に入学。しかしモノ作りへの情熱が冷めることなく大学を中退し、気がつけば大分行の夜行バスに飛び乗っていたという。
「その頃は京都に住んでいたんですが、妹から結婚して親許を離れる為、九州に帰って来て欲しいと言われたんですよ。そこで大阪の夜行バス乗り場に行くと、一番早い便が大分行だったんですよね。翌朝、大分県庁を訪ねて受付で『木工をやりたい』と言うと、『大分県日田産業工芸試験所(当時)』に行くように言われ、そこで木工製品を製造する師匠を紹介されたんですよ」。宮原さんは、その師匠の下で10年間修業した後に独立。以来、様々な木工製品を作ってきたが、現在は靴べらが面白いと、ポケットサイズからロングサイズまで、様々な靴べらを専門に製作しているという。
「靴べらは機能性だけでなくデザインも楽しめますからね。でも以前、この靴べらをイタリアに持っていったことがあるんですが、あまり反応がよくなかったんですよ。よく考えるとイタリアなどの西洋では家で靴を脱ぎませんよね。そう考えると、家はもちろん座敷のある飲食店などでよく靴を脱ぐ、日本でこそ靴べらが必要とされるんじゃないかと。そんな日本で靴べらを進化させたいと思う気持ちが強くなってきたんですよね」。そう語る宮原さんは、靴べらを一切の引っ掛かりのないスベスベした肌触りのモノへと進化させるのだが、それは手加工でなければ生まれないという。
「木は柔らかい部分と堅い部分が連続しているので、機械で仕上げると堅い部分を拾ってしまうので、どうしても微妙な引っ掛かりを拭うことが出来ず、デコボコになるんですよね。ですから、そうならないように仕上げる為には、人の手で徹底的に磨いていくしかないんですよ。今は3Dプリンターのようなモノもある時代ですから、私たち職人は機械で出来ないことを突き詰めていかないと、『いらないよ』と言われてしまいますからね。ですから絶対に機械に負けない手加工の技術を追求しようと。『実際の違いはどうなのか』と問われたら、それは本当にわずかなことなのかも知れませんが、そのわずかな違いが、必ずお客様に伝わると信じています」。手にした時の心地いい感覚や、ふと見た時に感じる良い雰囲気など、それらを備えた道具を普段、私たちは意識することもなく使っているが、そこには、わずかな部分にも妥協しない職人たちの手が必ず関わっている。そんな当たり前だが忘れがちなコトを、宮原さんの仕事は教えてくれた。
「師匠からは道具が使いやすいのは当たり前で、その上で美しいデザインがなければならないと言われてきたんですが、そのデザインも完成したと思った後に、もう一度頭を冷やして見直すと、また手を加えたくなるんですよね。そうやって無駄な部分を削ぎ落としていった先には、究極の靴べらが完成すると思うんですが、いつまで経ってもその繰り返しなんですよね。モノ作りの世界には完成はないのかも知れませんね」。そんな宮原さんは『3次元曲げ』と呼ばれる特殊な技法によって、木の表情を活かした靴べらを製作。それはただ道具としてのみならず、玄関を美しく彩るモノとしても人々を魅了していた。
「普通は木をU字に仕上げる場合は、窪んだ部分を削ることが多いんですが、私の場合は曲げるんですよね。そうすると木の繊維がそのまま残るので美しく仕上がりますし、何より木を無駄にしなくて済みますよね。今、木材が本当に乱暴に使われ過ぎていて、良い木がドンドン少なくなってきているんですよ。そんな急速に枯渇している貴重な木に報いる為には、やはり付加価値を付けてあげて、長く愛される品にすることが、我々、木を扱う職人の使命だと思っています」。そんな宮原さんの座右の銘はアメリカの作家、ジム・ドノヴァンの『これがあなたの人生だ。リハーサルではない』という言葉。自分の人生が幸せになるのも不幸になるのも自分次第と、自らの仕事に責任をもって歩む宮原さんの職人魂は、その靴べらのようにシャープかつ緊張感に溢れていた。
| 前のページ |